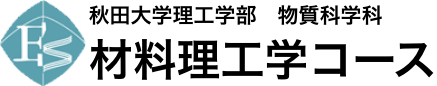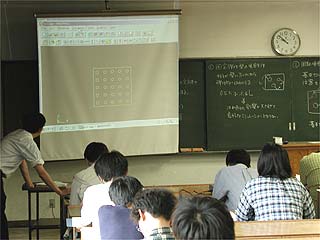皆さんが材料理工学コースにご入学されると、早速、数学、物理学、化学などの理工学の基礎的な科目と語学をはじめとする教養教育科目の授業を受けることになります。材料理工学コースの専門科目は、2、3年生で本格的に受けることになります。4年生になると2つの大講座内の各研究室に所属し、卒業研究に取り組みます。
以下では入学から卒業までに行われる材料理工学コースにおける教育について簡単にまとめてみます。
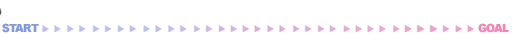
1.教養基礎教育(1年次)
語学(英語、フランス語、ドイツ語などから選択)にはじまり、経済学、政治学、体育、芸術科目などの文科系科目と、数学、物理学、化学など工学の基礎科目を学びます。また、物理学と化学の基礎的な実験や情報処理実習(コンピュータプログラミング)も行います。
材料理工学の授業としては「初年次ゼミ」という科目があり、材料理工学に関する重要な事項について学びます。
2.専門教育(2、3年次)
2年生になるといよいよ材料理工学の専門的な授業が本格的に始まります。まず金属材料およびセラミックス材料の物理的、化学的な性質を中心に勉強していきます。また、材料理工学に関する実験が始まります。
実験ではレポート(報告書)の提出が義務づけられており、これを書き上げることでよりいっそう実験内容の理解を深めます。さらに理論的な解析を行うときに必要な計算能力を養うために演習形式の授業も行われます。
ほとんどの授業が材料理工学コースの建物で行われますので、職員や先輩とのかかわりも深くなってきます。
3.創造工房実習(3年次)
3年生の後期になると、各研究室に所属して創造工房実習に取り組みます。この実習では、与えられた研究テーマに対して自分たちがアイデアをしぼりだし、さまざまな問題点を解決しながら自分で材料を作製したりします。
これまで、電池の自作やたたら製鉄という古代製鉄などが行われ、楽しみながら自分で考える力を養います。

▲創造工房実習風景(たたら製鉄)
【MOVIEはこちらから】
4.卒業研究 (4年次)
卒業まで残すところあと一年になると、所属する研究室で卒業研究に取り組みます。自分のテーマについて研究室の教官と議論を重ねたり、ときには友人と意見を交換したりして研究を進めていきます。各個人が材料を加工したり、コンピュータで実験装置を制御したり、特殊な装置を用いた測定を行ったりします。
このような経験を通して材料研究者、技術者となるための訓練を行います。2月には卒業研究発表会が行われ、これにパスすれば晴れて卒業となります。